前の記事
勝負は中2の春休みから始まっている?差がつく高校入試対策の進め方
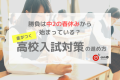
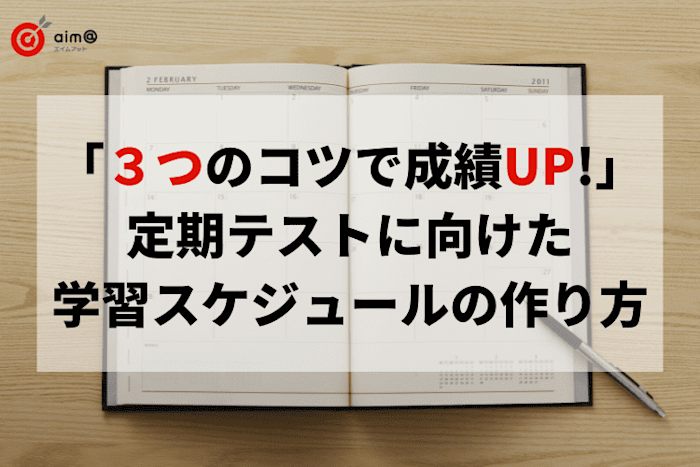
突然ですが、定期テスト対策の指導は戦略的に行えていますか?
生徒の定期テストの点数を向上させ、生徒や保護者からの信頼を高められるとうれしいですよね。
しかし、この記事を読んでいる先生の中には、こんな悩みを感じたことがある方もいるのではないでしょうか?
「定期テスト対策の指導は行っているものの、生徒の成績が思うように伸びない」
「生徒一人ひとりに十分な時間をかけて定期テストの指導をするのは困難」
そんなとき、一度見直していただきたいのが生徒の学習スケジュール�!
生徒が自主的に学習を進めつつ、定期テストで高得点を得るためには、効果的な学習スケジュールを用意することが非常に重要です。
今回は生徒が自主的かつ戦略的に、定期テスト対策を行えるようになる学習スケジュール作成のポイントを紹介します。
定期テストを控えた生徒と、ぜひ一緒につくってみてください!
もくじ
▼戦略的な学習スケジュールを作るポイント
1. 日ごとの勉強目標を立てる!
2. 前半は「インプット」、後半は「アウトプット」
3. 予備スケジュールで「できなかった」をなくす!
▼おわりに
最初にお伝えします。
戦略を練った学習スケジュールを作るのはとても大変...
ではありません!!
これからご説明する3つのポイントを抑えて頂ければ、効果的な学習スケジュールを簡単に作ることができます。
3週間前というのはあくまで目安です。
定期テスト対策は早ければ早いほど本番で有利に働きます。
しかし、宿題や部活で日々忙しい生徒にとって、定期テストを2週間より前から意識するのは難しいですよね。
そこで、意識を持たせるためにも、早めの対策を進めていくのが効果的です!
3週間前になったタイミングで、まずは定期テスト本番までの日ごとの勉強目標を立てましょう。
決めることは大きく2つです。
①どの日に何の教科を勉強をするのか
②その日に取り組む学習目標(ToDoリスト)
①どの日に何の教科を勉強をするのか
まずは大まかに、日ごとに取り組む教科を割り振りましょう。
ポイントは、
「範囲の広い教科」
「苦手の多い教科」
この2つを早い段階で時間に余裕をもって設定することです。
定期テスト本番が近づいて手遅れになる前に準備を進めましょう!
②その日に取り組む学習目標(ToDoリスト)
次に、その日に取り組む学習目標を設定しましょう。
ToDoリストをイメージしていただけると作りやすいです。
例えば英語であれば、
・単語帳p.50~p.80まで覚える
・Unit.4の長文を3回音読練習する
・授業プリントを2周読んで、現在完了の文法を復習する
といった形です。
ここでのポイントは、具体的な行動を目標に設定することです。
「単語を1時間勉強する」というような曖昧な目標にくらべて、目的意識をもって学習に臨めるようになるので、ぜひ取り入れてみてください!
学習スケジュールをきちんと進めていくうえで、毎日の課題とゴールの設定は非常に重要です。
もちろん変更はOK!
必要に応じて修正しながら学習を進めていきましょう。
定期テストの点数を上げる一番の方法はアウトプットを増やすこと。
多くの先生はご指導の中でアウトプットの重要性を実感されているのではないでしょうか。
定期テストにおいても同じことが言えます。
それでは、どのようにインプットとアウトプ��ットを学習スケジュールに盛り込んでいけばよいのでしょうか。
ここでおすすめするのは、
テスト2週間前より前は「インプット」に注力し、
2週間前より後は「アウトプット」に注力する学習スケジュール
です。
その理由として、この項目では「2つの比率」についてお話しします。
①3:7の法則
このような実験があります。
コロンビア大学の心理学者アーサー・ゲイツ博士が小学3年生から中学2年生までを対象に、人物プロフィールを暗唱させました(※1)。
この実験の中で最も高得点を出したのは、与えられた時間のうち約30%をインプットに使い、残りの約70%をアウトプットの時間にしたグループだったのです。
勉強時間を増やしても定期テストの点数が上がらない多くの生徒に見られる特長は、暗記やノート整理にばかり時間をかけていること。
つまり「インプット」中心の学習スタイルに陥っていることです。
学習スケジュールを作る際は、
「インプットは3割、アウトプットは7割」
この比率を意識してみてください。
②1:5の法則
この数値は、
「勉強をしてから復習するまでの期間:復習をしてから試験までの期間」
の最適な数値です。
こちらも、アメリカの研究グループが2008年に発表した論文で明らかになっています(※2)。
「勉強をしたらすぐ復習!」
という生徒のやる気は素晴らしいですが、実は時間を置いて勉強することに意味があるのです。
例えば試�験までの期間が18日の場合、
勉強をしてから1回目の復習をするまでの期間を、3日とするのがベストになります。
復習をしてから試験までの期間が15日で、「1:5」となるためです。
2回目以降の復習日は、そこから試験日まで3日の間隔で行えばOKです!
以上の2つを踏まえると、
「テスト3週間前はインプット」
「テスト2週間前以降はアウトプット」
に注力する学習スケジュールが効果的です!
ただ、インプットとアウトプットどちらか一辺倒になる必要は全くありません。
提出物の進み具合などとも相談しながら、無理のない学習スケジュールにしていきましょう。
==================
定期テストに向けたアウトプットを増やしたい!
でも十分に演習させられる教材がない...
そんなお悩みをお持ちの先生におすすめしたいのは、弊社が提供する『aim@』!
搭載問題数は13万以上。実技教科も加わり、9教科対策が可能です!
▶︎詳しい資料はこちらから無料ダウンロード
==================
「スケジュールは作るんだけど、なかなかそれ通りに進まないなぁ...」
生徒の勉強に限らず、ご自身にもこんな経験はありませんか?
スケジュール通りに進まない時の焦りは、丁寧さを欠いたりやる気を消失させたりするもの。
せっかく学習スケジュールを作っても、これでは逆効果です。
そうなる前におすすめしたいのは、「予備スケジュール」を作っておくこと。
作り方は至って簡単。
予備日もしくは予備時間を学習スケジュールに組み込むことです!
例えば、
「塾の授業がない木曜日を予備日にする」
「学校のない土曜日の午前中を予備時間にする」
という形で、全体のスケジュールの中で確実に時間に余裕があるところを選ぶと良いでしょう。
もし予備のスケジュールが必要なくなったら、勉強を進める中で「もう少し勉強したい!」と思う範囲を復習する時間にしましょう。
勉強をほどほどに、リフレッシュする時間にしても良いですね。
自主学習はスケジュール通りに進まないもの!
そう割り切って、あらかじめ予備スケジュールを作っておきましょう。
いかがでしたでしょうか。
ここまでご説明したポイントをまとめると、
1.3週間前から日ごとの勉強目標を立てる!
2.前半は「インプット」、後半は「アウトプット」
3.予備スケジュールで「できなかった」をなくす
となります。
繰り返しになりますが、戦略的な定期テスト対策を行うためには、生徒が自主的に取り組める学習スケジュールをつくることが重要です。
ぜひ今回ご説明したことを活かして、高得点を目指していきましょう!!
【参考資料】
※1 Jeffrey D Karpicke,Henry L Roediger 3rd
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18276894/
※2 Nicholas J Cepeda ;et al.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19076480/