前の記事
入塾説明の「あるある失敗例」6選!営業トークの改善ポイントを解説
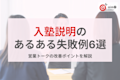
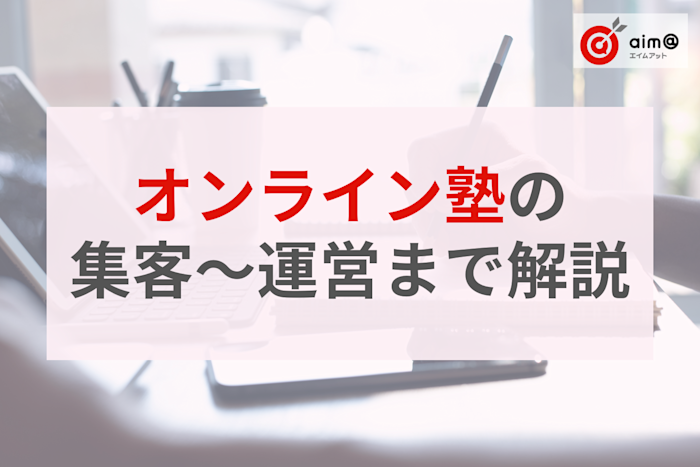
近年、働き方や学び方の多様化に伴い、オンライン塾への関心が高まっています。
特に個人で学習塾を経営されている方にとっては、商圏の制約を超えて新たな生徒を獲得できるチャンスであり、また、コロナ禍以降変化した学習ニーズに対応する手段としても有効です。
しかし、
「オンライン塾って本当に儲かるの?」
「どうやって生徒を集めればいいの?」
「既存の塾とどう両立させれば…」
といった疑問や不安をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
本記事では、オンライン塾の立ち上げから運営、集客に至るまでの具体的なノウハウを、事例を交えながら徹底解説します。
オンライン塾導入を検討している、あるいは既に始めたものの課題を感じている個人塾経営者の皆様にとって、成功への道筋を見つける一助となれば幸いです。
※この記事は、2025年5月21日に開催したセミナーの内容を元に作成したものです。
オンライン塾には、従来の対面式塾にはない多くのメリットがある一方で、特有のデメリットも存在します。
まずはこれらを正しく理解し、対策を講じることが成功の第一歩です。
通塾不要・効率的な学習: 生徒は自宅など好きな場所で受講できるため、通塾にかかる時間や労力を削減できます。移動時間を学習時間に充てられるため、勉強効率の向上が期待できます。
全国への商圏拡大: 地理的な制約がないため、日本全国、あるいは海外の生徒も対象にできます。これまでアプローチ�できなかった層にもリーチ可能です。
多様な講師マッチング: 全国から優秀な講師を採用できるため、特定の専門分野に強い講師や、生徒の志望校出身の講師など、多様なニーズに対応したマッチングが実現しやすくなります。
固定費削減(賃料など): 物理的な教室が不要なため、家賃や光熱費といった固定費を大幅に削減できます。
地域格差是正への貢献: 地方にいながら都市部の質の高い教育を受けられるなど、教育の地域格差解消に貢献できる可能性があります。
学習管理の難しさ
対面と比べて生徒の学習状況を把握しにくく、自己管理が苦手な生徒は集中力が途切れたり、学習が滞ったりする可能性があります。
<対策>
手厚いフォロー体制の構築(定期的な進捗確認、個別面談)、学習管理ツールの導入、オンライン自習室の提供などで、生徒のモチベーション維持と学習習慣化を支援します。
保護者からの見え方(誤解)
自宅学習が中心となるため、保護者からは「本当に勉強しているのか」「サボっているのではないか」と不安視されることがあります。
<対策>
定期的な学習状況の報告、保護者面談の実施、オンラインであっても学習の様子を伝える工夫(授業の録画共有など)を通じて、保護者とのコミュニケーションを密にし、信頼関係を構築します。
看板効果がないことによる集客の難しさ
地域密着型の塾とは異なり、「看板を見て問い合わせ」といった集客は期待できません。
<対策>
WebサイトやLP(ランディングページ)の作成、SEO対策、SNS活用、オンライン広告など、インターネットを駆使した集客戦略が必須です。
「塾は通うもの」という固定観念
特に保護者世代には、依然として「塾は教室に通って学ぶもの」という固定観念が根強く残っている場合があります。
<対策>
オンライン塾ならではの価値(効率性、個別最適化された指導など)を明確に伝え、成功事例や生徒の声を積極的に発信することで、オンライン学習への理解と信頼を深めます。
指導のしづらさ(対面比較)
生徒の表情や細かな反応が読み取りにくい、ノートや手元の資料を直接確認できないなど、対面に比べて指導が難しい側面があります。
<対策>
画面共有機能、ホワイトボード機能、チャット機能など、オンラインツールの特性を最大限に活かした指導方法を工夫します。また、カメラONを推奨するなど、コミュニケーションを取りやすい環境づくりも重要です。
「オンライン塾は家賃もかからないし、簡単に儲かりそう」と考えるのは早計です。
実際には、価格競争の激化、生徒の継続率の低さ、マーケティングコストの高騰、他塾との差別化の難しさ、スケールメリットの得にくさといった課題があり、安易な参入は失敗に繋がりかねません。
しかし、これらの課題を克服し、「儲かるオンライン塾」を実現するための鍵が5つあります。
LTV(顧客生涯価値)の高い仕組みを持つ
単発の受講で終わらせず、長期的に継続利用してもらう��ための仕組み作りが重要です。例えば、高校受験コースから大学受験コースへの内部進学を促したり、低学年から長期的にサポートできるようなカリキュラムを設計したりするなどが考えられます。
また、ターゲットとする学年を広げることで、LTV向上も期待できます。
強力なブランディングとカリスマ講師の育成
「〇〇先生に教わりたい」「この塾の指導方針に共感できる」といった、価格以外の魅力で選ばれる塾を目指しましょう。
そのためには、塾独自の強みや指導メソッドを明確にし、それを体現するカリスマ的な講師を育成するか、経営者自身が広告塔となって積極的に情報発信することが有効です。
YouTubeやSNSでのファン作りも効果的です。
手厚い学習管理と進捗フォロー
オンラインの弱点である「生徒が継続しにくい」点を補うためには、徹底した学習管理と進捗フォローが不可欠です。
定期的な個別コーチング、毎日の進捗確認、迅速なチャット対応など、生徒との接触頻度を増やし、学習の習慣化をサポートします。
生徒マネジメントの質が、オンライン塾の成否を分けると言っても過言ではありません。
高単価・高付加価値サービスの提供
安価なサービスだけでは利益を確保しにくいのが現状です。
医学部専門コース、特定の難関校対策コース、オーダーメイドの学習プランなど、特定のニーズに応える高付加価値なサービスを提供することで、客単価を上げることが可能です。
また、受験直前期の集中指導なども効果的です。
独自プラットフォーム/教材による利益率向上(また�はICTサービスの活用)
自社で学習プラットフォームや独自教材を開発・提供できれば、手数料を削減し利益率を高めることができます。
ただし、開発には大きなコストと時間がかかるため、小規模な塾の場合は、既存の優れた学習塾向けICTサービスを賢く活用することも有効な手段です。
>低コストで始められる!学習塾向けのICT教材『aim@(エイムアット)』の資料請求はこちらから
これら5つの鍵の中でも、特に「2. ブランディング」と「3. 学習管理」は、入塾率と継続率に直結する非常に重要な要素です。
オンライン塾の集客は、インターネットを主戦場とするため、戦略的なマーケティングが不可欠です。
ターゲティング: どの学年の生徒を対象とするか、生徒本人と保護者のどちらにアプローチするかを明確にします。
認知獲得: SNS(YouTube、X、Instagramなど)の活用は必須です。これに加えて、Web広告(Google広告、Meta広告など)を組み合わせることで、より広範囲な認知獲得を目指します。
訴求: 誰に、どのタイミングで、どのようなメッセージを伝えるかを設計します。
クロージング: オンライン塾は全国に競合がいるため、リアル塾よりも成約率が低くなる傾向があることを念頭に置き、丁寧な対応を心がけます。
Google広告(リスティング広告など): 「〇〇大学 受験塾」のように、具体的なキーワードで検索し��ている顕在層にアプローチできるため、比較的高い成約率が期待できます。
Meta広告(Instagram、Facebook広告): 親世代への訴求に強く、画像や動画を用いた視覚的なアピールが可能です。
YouTube広告: 動画を通じて塾の雰囲気や指導の様子を伝え、信頼感や実績をアピールできます。
TikTok広告: 若年層への認知拡大には有効ですが、直接的な問い合わせ(コンバージョン)には繋がりにくい傾向があります。
SNSは、広告効果を高める上でも、ファンを育成し継続的な集客に繋げるためにも極めて重要です。
特にYouTubeは、オンライン塾との親和性が高いプラットフォームと言えるでしょう。
ステップ1:YouTubeチャンネルのポジショニング設計
ターゲット明確化: 「誰に何を伝えたいのか」を徹底的に考え、ペルソナ(具体的な顧客像)を設定します。「医学部志望の高校生向け」「定期テストで平均点以下の成績に悩む中学生向け」など、ターゲットを絞り込むことで、メッセージが響きやすくなります。
コンテンツ軸の設定: 発信するテーマを3~4つ程度に絞り込み、「このチャンネルを見れば〇〇が分かる」という専門性を打ち出します。
ステップ2:集客につながる動画コンテンツ設計
フックの強いショート動画で認知拡大: まずは短い動画(YouTubeショート、Instagramリールなど)で、最初の数秒で視聴者の心を掴む「フック」の強いコンテンツを発信し、チャンネルの存在を知ってもらいます。
ロング動画での�信頼獲得とリード獲得: ショート動画で興味を持った視聴者を、より詳しい情報やノウハウを提供する長尺動画へ誘導します。動画の最後や概要欄で、無料の学習資料プレゼントなどを通じて公式LINEやメルマガへの登録を促し、見込み客リストを獲得します。
SNS運用代行への注意点: ゼロからチャンネルを立ち上げる場合、最初から運用代行会社に丸投げするのではなく、まずは塾の強みや想いを理解している内部の人間が中心となってコンテンツを作成し、PDCAを回していくことが重要です。
ステップ3:動画内のCTA(コール・トゥ・アクション)
動画の視聴者に「次に何をしてほしいか」を明確に伝えます(例:「詳しくは公式LINEへ」「無料体験はこちら」)。
ただし、宣伝色が強すぎると視聴者が離れてしまうため、特にショート動画ではCTAを控えめにするか、コンテンツの最後に自然な形で挿入するなどの工夫が必要です。
ステップ4:受け皿(リスト獲得ページ)の設計
獲得したリスト(見込み客)との継続的な接点を持つために、LINE公式アカウントやメールマガジンを必ず用意します。
登録特典(限定動画、学習計画シートなど)を提供することで、登録のハードルを下げ、ブロックを防ぎます。
ステップ5:クロージングまでの導線設計
LINEやメルマガで、定期的に役立つ情報や限定コンテンツを発信し、見込み客との関係性を深めます(ナーチャリング)。
適切なタイミングで、個別相談会や体験授業の案内、期間限定のキャンペーンなどを告知し、入塾へと繋げます。ZoomやGoogle MeetなどのWeb通話ツールを活用した個別相談は、クロージングにおいて非常に有効です。
既存のリアル塾を運営している場合、オンライン塾をどのように位置づけるかは重要な戦略となります。
オンライン塾に向いている生徒像
部活動や学校行事で忙しく、決まった時間に通塾するのが難しい生徒
自分のペースで学習を進めたい自立型の生徒
近隣に通いたい塾がない、または特定の講師の指導を受けたい生徒
移動時間を学習時間に充てたい効率重視の生徒
リアル塾(対面指導)に向いている生徒像
学習習慣が身についておらず、ある程度の強制力が必要な生徒
自宅では集中できず、学習環境を重視する生徒
先生に直接質問したり、細かく指導してもらったりすることを好む生徒
特に、中学受験の小学生や、きめ細やかなサポートが必要な受験直前期の生徒
既存の塾にオンラインコースを併設する場合、まずは遠方の生徒や、上記のオンライン塾向きの特性を持つ既存の生徒に案内してみることから始めるのが良いでしょう。
また、リアル塾の強みである「直接的なコミュニケーション」とオンラインの「効率性」を組み合わせたハイブリッド型の指導も有効です。
オンライン塾は、適切な戦略と実行力があれば、個人経営の学習塾にとっても大きな成長の機会となり得ます。
�オンライン塾成功のポイント
オンラインのメリットを最大限に活かし、デメリットへの対策を徹底する。
LTV向上、ブランディング、手厚い学習管理、高付加価値サービス、利益率向上という「5つの鍵」を意識する。
ターゲットを明確にし、Web広告とSNSを戦略的に活用した集客を行う。
既存のリアル塾との棲み分けや連携を考慮する。
本記事でご紹介したノウハウは、あくまで成功のための一例です。それぞれの塾の強みや状況に合わせて、最適な形を模索していくことが大切です。
オンライン化への挑戦は、決して簡単な道のりではないかもしれませんが、新たな可能性を切り拓く大きな一歩となるはずです。
この記事が、皆様のオンライン塾成功の一助となれば、これほど嬉しいことはありません。
=========================
学習塾向けICT教材『aim@(エイムアット)』は、20種類以上の教材が使い放題のサービスで、低コスト&生徒1名からでも始められます。
オンライン塾様からのお問い合わせも増えており、実際にご活用いただいている先生からは、
「オンラインでも生徒の進捗管理がしやすくて便利」
「必要に応じて教材を追加したり、使わない時期は減らしたりできるのがありがたい」
「正答率が100%になるまで繰り返しやるよう指示したら本当に点数が上がった」
などなど、嬉しいお声をたくさんいただいております。
ご興味をお持ちいただけましたら、お気軽にお問い合わせください!
>��学習塾向けICT教材『aim@(エイムアット)』の資料請求はこちらから