前の記事
ICT教材で実現!講師1人で9教科対応を可能にする指導の仕組み

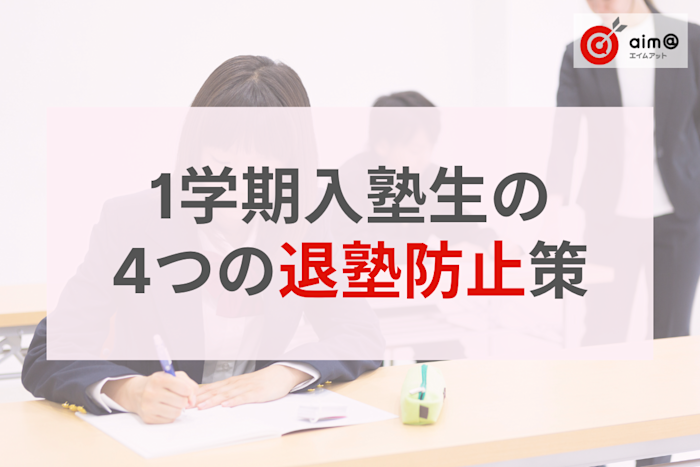
「春から夏にかけて生徒が増えたものの、毎年、2学期が終わる頃には何人か辞めてしまう…」
「せっかく集めた新入生の定着率をなんとか上げたい」
多くの塾経営者の先生方が、このような悩みを抱えていらっしゃるのではないでしょうか。
せっかくご縁があって入塾してくれた生徒が塾を去ってしまうのは、経営的な観点だけでなく、精神的にも辛いものです。
生徒の退塾は、いくつかの「予兆」を経て起こります。
そのサインを見逃さず、早期に対策を打つことができれば、防げるケースは少なくありません。
この記事では、1学期に入塾した生徒が辞めてしまう主な理由を分析し、明日からすぐに実践できる具体的な4つの退塾防止策について解説します。
生徒が退塾を決意する背景には、必ず何らかの理由が存在します。
特に新しい環境に慣れていない1学期の生徒は、些細なことがきっかけで不安を感じやすいものです。
最も多いのが「授業についていけない」という学力面の不安です。
入塾当初はやる気に満ちていても、少しず�つ学校の授業との進度のズレや、思ったように成績が上がらない現実に直面し、「自分だけができていない」という孤立感を深めてしまいます。
この小さなつまずきを放置してしまうことが、退塾の大きな引き金となります。
生徒は、先生が自分のことをどれだけ気にかけてくれているかを敏感に感じ取ります。
「先生は自分の名前や苦手な単元を覚えてくれている」
「自分の頑張りを認めてくれている」
という実感がないと、生徒の塾への所属意識は徐々に薄れていきます。
最終的な意思決定者である保護者が「この塾に通わせていて、本当に効果があるのだろうか?」という不安を抱えているケースも非常に多いです。
塾での子どもの様子が分からなかったり、学習成果が目に見えなかったりすると、保護者の不満は募ります。
子ども自身は塾に満足していても、保護者の判断で退塾に至ることも少なくありません。
では、これらの原因に対して、具体的にどのような対策を打てば良いのでしょうか。
特別な設備や多額の費用は必要ありません。
塾長先生や講師の方々の少しの意識と工夫で、生徒の定着率は大きく変わります。
「できた!」という実感は、生徒のモチベーションの源泉です。
いきなり高い目標を掲げるのではなく、その生徒のレベルに合わせた「あと少し頑張ればクリアできる」課題を与え、達成できたら具体的に褒めることを徹底しましょう。
「〇〇さん、この前の小テスト、苦手な関数の問題が解けていたね!すごいぞ!」
このような具体的な声かけ一つで、生徒は「先生は自分のことを見てくれている」と感じ、学習への意欲を取り戻します。
全生徒と毎日じっくり話すのが難しくても、コミュニケーションを仕組み化することは可能です。
例えば、授業の終わりに「1分間チェックイン」の時間を設けるのはいかがでしょうか。生徒が帰る際、一人ひとりとほんの少しだけ対話する時間をルール化するのです。
講師は、「今日の授業で一番わかったことは?」「何か不安なことはない?」といった短い声かけを通じて、生徒一人ひとりの表情や声のトーンから、その日のコンディションを直接感じ取ります。
このわずかな時間の積み重ねが、生徒に「先生は自分を気にかけてくれている」という強い実感と、小さなつまずきをすぐに相談できる安心感を与えます。
保護者の不安を解消するには、定期的な情報提供が最も効果的です。
電話や面談が難しくても、月に一度、メールや連絡アプリで以下のような簡単なレポートを送るだけでも印象は全く違います。
今月の学習単�元と進捗
小テストの結果や理解度
塾での様子(「集中して取り組んでいます」「〇〇さんと楽しそうに話していました」など)
客観的な事実と、少しの主観的なポジティブ情報を伝えることで、保護者は安心して塾に子どもを預けることができます。
▼保護者満足度を向上させる「指導の見える化」に関する記事はコチラ
「塾に友達がいる」という事実は、生徒が塾に通い続ける強力な動機になります。
特に新しい生徒が孤立しないよう、歓迎会や季節のイベント、あるいはグループ学習の機会などを設け、生徒同士が自然と交流できる場を作りましょう。
「勉強を教え合う仲間」や「休憩時間に話せる友達」の存在が、塾を「行かなければならない場所」から「行きたい場所」へと変えてくれます。
生徒の退塾を防ぐために最も重要なのは、生徒・保護者との間に「信頼関係」を築くことに他なりません。
そして、その関係構築は、講師個人の頑張りだけに頼るのではなく、塾全体で「仕組み化」することが大切です。
今回ご紹介した具体的な退塾防止4つのアクションは以下のとおりです。
「小さな成功体験」を意図的に演出する
授業後の「1分間チェックイン」で個別に声をかける
保護者への「安心報告」を月1回、仕組み化する
生徒同士の「横のつながり」をサポートする
日々の業務に追われる中で、新たな取り組みを始めるのは大変に感じられるかもしれません。
しかし、今回ご紹介したような心の通ったコミュニケーションの積み重ねこそが、大手塾には真似のできない、先生の塾ならではの強みであり、価値となります。
まずは、本日ご紹介した4つのアクションの中から、一つでもご自身の塾で取り入れられそうなものから始めてみてください。
その小さな一歩が、生徒と塾との絆を深め、来年、再来年へと繋がる大きな財産となるはずです。
